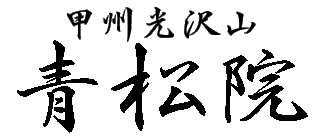
|
【心の杖言葉】
ホモレリギオースス(宗教の人)



|
|
|
【山内より】 令和7年8月7日午後4時30分より 本堂にて先祖供養、新盆塔婆供養が本年も厳修されます。ご参加ください。 (令和7年7月)  令和7年4月8日 本年も園児、お坊さん、ご父兄、檀信徒、皆様の御力により「花祭り」を厳修することができました。
(令和7年4月)
令和7年4月8日 本年も園児、お坊さん、ご父兄、檀信徒、皆様の御力により「花祭り」を厳修することができました。
(令和7年4月) 8月7日(水)先祖供養法要が行われました。併せて新盆塔婆供養も厳修されました。
8月7日(水)先祖供養法要が行われました。併せて新盆塔婆供養も厳修されました。(令和6年8月) 

涅槃会・豆まきの様子です。 光の森こども園の良い子のみなさんは、江戸時代狩野派の文化財(涅槃図 江戸時代寛文元年・西暦1661)をお行儀よく鑑賞できました。 また、豆まきもお友達と喧嘩せず仲良く拾うこともできました。おりこうさんでした。 (令和6年2月) 

|
|

|
◇ 予定表 NEW! ◇ 歴史 ◇ 系譜 ◇ 観音信仰 ◇ 庭園 ◇ 仏像 ◇ 仏舎利 ◇ 彫刻作品集 ◇ 心の杖言葉(連載中) ◇ 仏典に学ぶ ◇ 山内より ◇ 各種御相談・問合せ ◇ 墓地・葬儀・永代供養の御相談 |
|
曹洞宗光沢山 青松院 〒400-0075 山梨県甲府市山宮町3314 地図参照 TEL 055-251-6812 / 055-252-6871(光の森こども園・共通) <電車/バスでのアクセス> JR中央線・身延線 甲府駅下車約4キロ 山梨交通山宮循環バス「山宮北」下車(約10分) <車でのアクセス> 中央高速道甲府昭和インターより15分 湯村交差点を北に入る 中央高速道双葉スマートICより15分 |
|