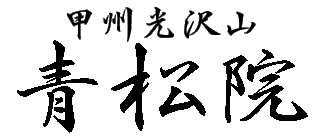
|
【心の杖言葉】
ホモパティエンス(受苦の人、忍苦の人、しのぶ人・・・)
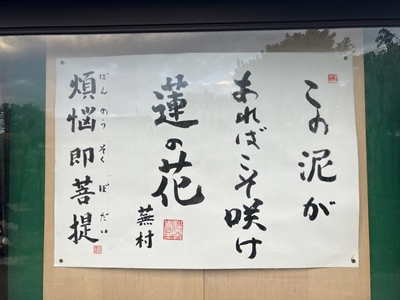

「ホモレリギオースス(宗教の人)」 「ホモヴィアトール」 「柔軟心是道(ニュウナンシンコレドウ)」 「光あるうちに光の中を歩め」(トルストイ) 「鳥飛んで鳥の如く歩け」 「正師を得ざれば学ばざるに如かず」(学道用心集) 「エーレン、ヴエーレン」(ゲーテ、西東詩集からの言葉) 「大愚難到志難成」(夏目漱石) 「ステイハングリー、ステイフーリッシュ」(スティーブ・ジョブズ) 「菩薩行」 「辛抱という棒を一本建てよ 忍辱(六波羅蜜)」(板橋興宗禅師) 「愛情の温度計」 「何故なし!」(シレジウス) 「罪障の山高く 生死の海深し」(柏崎 地謡より) 「時時の初心忘るべからず」(花鏡) 「悟りといふ事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であった」(病床六尺) 「放てば手に満てり」(弁道話) 「仏道を習うというは 自己を習うなり」(現成公案) 「道は虚にとどまる 虚とは心斎なり」(荘子・人間世篇) 「至人之用心若鏡 不将不迎 應而不蔵」(荘子・応帝王篇) 「壺中日月長」 「少くして学べば 壮にして成すあり」(言志四録) 「而今の山水は古佛の道現成なり 朕兆未萌の自己なるがゆゑに現成の透脱なり」(山水経) 「過則勿憚改」(論語学而) 「西行の和歌における、宗祇の連歌における、雪舟の絵における、利休が茶における、その貫道するものは一なり」(笈の小文) 「岐路こそまさに愛すべし」(楊朱) 「朝(アシタ)に道を聞かば 夕べに死すとも可なり」(論語 里仁から) 「億劫相別而須臾不離(億劫に別れて須臾も離れず)」(大燈国師) 「苦悩を貫き 歓喜に至れ」(Beethoven) 「春は花 夏ほととぎす 秋は月 冬雪さえて すずしかりけり」(傘松道詠) 「よろこびは ひゃくぶんのいちの しんいっぽ」(虚仮子) 「人生はいばら道、されど宴会」(樋野興夫) 「念ずれば花ひらく」(坂村真民) 「生きるとは 死ぬときまでの ひと修行」 「為君幾下蒼龍窟(君がため幾たびか下る蒼龍窟)」 「衆生無辺誓願度(しゅじょうむへんせいがんど)」 「されば、人、死を憎まば、生を愛すべし。存命の喜び、日々に楽しまざらんや。」(吉田兼好) 「希望 工夫 気迫 感謝」(松原泰道) |
|